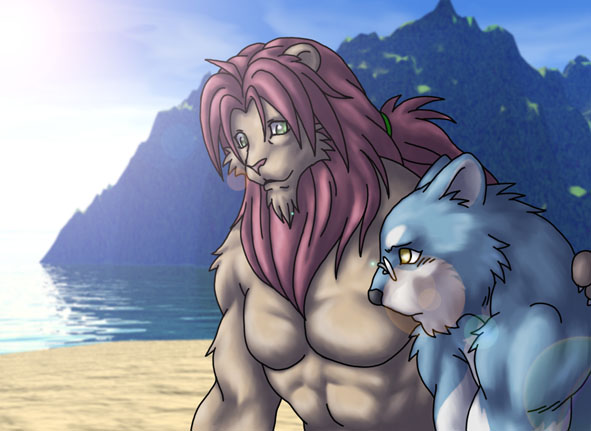海へ
僕はバイトまでの余った時間で学校へときていた。
僕の名はバーツ。
あまり信じてもらえないが現在は某有名大学医学部の5年生。
いいかげん将来のことを少しずつでも考えていくべき時期だ。
そう思い、何かないかと学校へ来てみたが、何の目的もないものに何かを与えてくれるほど
休日の学校は優しくはない。
結局僕はなんの収穫も得ないまま掲示板の前で大きく溜息をついた。
「よお、バーツじゃないか。」
言葉とともに誰かが僕の方をぽん、と叩く。
力なく振り返ればそこには大柄な虎獣人の姿。
「あ、アトラ先輩・・・。」
先輩、というが現在は同じ学年。
彼が留年したことにより現在は机を並べて勉強する立場となっている。
『先輩』と言うのはあだ名みたいなもので、
気さくな人柄なこともあり皆からそう呼ばれ慕われている。
「ちょうど良かった。お前に連絡しようと思ってたんだ。」
「え?」
僕とアトラ先輩は掲示板の前から移動し、手近な人気のない教室にやってきていた。
「アメリカ・・・ですか?」
「ああ。やっぱり本場で勉強したいと思わないか?」
アメリカ・・・。
ぼんやりとした頭で僕はそれを考えていた。
アトラ先輩が、一緒にアメリカに行かないかというのだ。
そもそも医学の最先端を学びたいと思っても、この国にいてはそれはかなわない。
アトラ先輩はそれを不満に思い、なんとかアメリカで勉強を、と常々思っていたらしい。
そして、一緒に海外へとわたるはずだった友人が突然ダメになったらしい。
僕にお誘いがかかったのはそう言うわけだった。
「確かに・・・行って見たいとは思いますけど・・・。」
僕はアメリカでの生活を思い描いた。
新しい友人や新しい環境。
何よりも最先端をいくであろう勉強。
それらは非常に魅力的だ。
だけど。
『ポン太。』
僕の頭の中に、心地よい音が響いた。
そう、ドル先輩の声。
アメリカに渡るということはドル先輩にあえなくなるということだ。
「どうした?」
アトラ先輩が心配そうにこちらをのぞきこんでくる。
「いえ・・・。」
僕は視線をそらしながらそう言った。
考えてみれば、これはチャンスかもしれない。
先輩にずっと憧れる日々。
ずっと片思いを続ける日々。
これを終わらせる、チャンスかもしれない。
「・・・まあ、今すぐ答えを聞きたいって訳じゃなくてだ」
「行きます。」
僕のことを気にかけてくれたアトラ先輩の台詞をさえぎって、僕はそう答えた。
「あ・・・行くの。」
先輩が間抜けな顔をして答えた。
「行きます。」
そのとき僕の頭に浮かんでいたのは、ドル先輩とミールさんの笑顔。
僕といるときよりも嬉しそうなドル先輩の笑顔だった。
「海、行きませんか?」
僕の言葉に三人は『え?』と書いた顔をこちらに向けた。
ドル先輩、ミールさん、シオンさんの三人。
僕は彼らをとある喫茶店に呼び、そう持ちかけたのだ。
「ずいぶん唐突だね・・・。」
そう言って紅茶を口に運ぶミールさん。
「まあでも、いいんじゃないですか?私もしばらく海なんて行ってませんし。」
シオンさんはそう言って僕に賛同してくれた。
ミールさんも賛同するように頷いてくれる。
後は、肝心のドル先輩。
先輩は少し考えて口を開いた。
「いいんじゃねえか。あんまり金はねえけどな。」
僕はその場で小躍りせんばかりに喜んだ。
これでドル先輩と旅行にいけるのだ。
「じゃあ、じゃあ僕父に車借りてきますね!」
喜びに弾む声を抑えつつ僕はそう言った。
「いや、車なら私のに乗ればいいよ。」
シオンさんが笑顔でそう言ってくれた。
「それなら、せめて運転手は僕がやりますね。
道も大体わかりますし。」
僕の言葉に三人が頷く。
まあ、この中では最年少であるわけだし当然といえば当然だ。
「それから、夜は温泉行きましょう。
僕が小さい頃父に連れて行ってもらったところで、いい旅館があるんです。」
これは僕のとっておき。
旅館の雰囲気や値段、サービス内容を説明すると三人もすぐに賛成してくれた。
「水着以外に持っていくものってあるかな?」
ミールさんが今までに決めたルート、かかる費用、持ち物を整理してメモにしている。
僕は少し考えて答えた。
「まあいざとなったら買えますし・・・最低限必要なのってそれと着替えと、くらいじゃないですか?」
ドル先輩とシオンさんも考えているが、特に思い浮かぶものはないらしい。
「後は日程だな。俺はいつでもいいぞ。」
もちろん言い出しっぺの僕はいつだって構わない。
ミールさんとシオンさんの予定をあわせ、結局出発は二日後の早朝に決まった。
そして約束の日の朝。
僕、先輩、ミールさんの三人はシオンさんの家の前に集合していた。
僕達三人はシオンさんの家を見上げている。
相変わらず大きい家だなあ・・・。
「すまない、待たせてしまったね。」
その言葉に僕が振り返るとベンツから降りてくるシオンさんの姿があった。
「うわぁ・・・。」
思わず声が漏れた。
僕でも知ってる一流高級車。
隣では先輩とミールさんもベンツの持つ圧倒的な存在感に気おされている。
「これ、僕が運転していいんですか?」
「ああ、もちろんだよ。」
その言葉に僕は恐る恐る運転席に乗り込む。
シオンさんがミールさんを促し、二人で後部座席へと乗りこんだ。
残るドル先輩は助手席に座ることになる。
シオンさんが気を回してくれたのだ。
その心遣いに嬉しくなりながら、僕はキーに手を伸ばしそれを捻った。
ぶるん、と音がして車全体が小さく揺れる。
「それじゃあ出発しますねー。」
エンジンが温まるまでしばらく待つと、僕はおもむろにアクセルを踏み込んだ。
『っうわぁぁぁっ!』
一瞬間をおいて三人の悲鳴がはもった。
予想外の悲鳴に僕は少し驚く。
「どうしたんですか?」
『スピード落とせっ!』
三人の声が唱和する。
息、ぴったりだなあ。
そう思いながらメーターに目をやる。
速度は時速90キロ。
そんなにでてないじゃん。
「前みろーっ!」
ドル先輩が前を指差して叫んだ。
「おっと」
僕は軽くハンドルを切ると目の前に迫った塀を90度カーブすることで避けた。
ぎゃぎゃぎゃっ、とタイヤと地面がこすれる音が聞こえる。
さすが高級車、聞こえる音が小さい。
『わあぁぁっ!』
曲がる際に先輩とシオンさんの悲鳴が再び響いた。
ミールさんはといえば、既に1人で眠りに入っている。
乗り物に弱いのかなあ。
「赤だーッ!」
先輩は信号を指差しながらそう叫んだ。
そういわれてみれば、今通り過ぎた信号は赤かったような気もする。
まあ、過ぎたことは気にしない。
「ひと、ヒトをはねるぞッ!」
今度はシオンさんが叫ぶ。
確かにわき道に人影がある。
僕は迷わずハンドルを切った。
「お、おおお・・・。」
思わず僕の口から声が漏れた。
何処でどうなったのか。
僕の運転している車は右半分のタイヤだけで走っていた。
片輪走行、という奴だ。
視界が傾く。
「ポン太ーっ!元にもどせーっ!!」
シートベルトをしていなかった先輩は僕の方にずり落ちながらそう叫んだ。
先輩の手が僕の肩に触れる。
こういうの、役得っていうんだろうなあ。
そう思いながら僕は先輩の方に身体を寄せ、
なんとか全員が体重移動することで車を正常な状態に戻す。

「車線ーっ!!」
シオンさんの叫びは何時もの冷静さの片鱗もうかがえなかった。
みんな結構細かいんだなあ。
僕はハンドルを右に、左にと回しながらなぜか正面から走ってくる車を左右に交わしながら走った。
『ぶつかるっ!』
再び聞こえる二人の叫び。
正面からは大きなタンクローリー。
僕はハンドルをきり、迷わず歩道に乗り上げると地下道へもぐる通路の屋根を走った。
そのまま、車は宙を舞う。
結局、シオンさんがトイレに行きたいと言い出してSAに止まるまで二人の悲鳴は響いていた。
ミールさんは相変わらず車の中で寝ているし、ドル先輩はSAにつくなり車から降りてベンチのうえでぐったりしている。
シオンさんはふらふらとした足取りでトイレに消えたままだ。
僕は自販機で冷たい飲み物を買うと先輩に手渡した。
「乗り物、弱いんですね。」
僕の言葉に先輩はぴくりと身体を動かすが、それだけで動きは終わる。
何時もはぴんとたった耳がしゅんと、下に向かって垂れている様子はなんだかかわいい。
思わず撫でたくなるかわいい頭を見ていると、シオンさんがふらふらと戻ってきた。
「ば、バーツ・・・。運転は私がするよ。」
「でも・・・顔色悪いですよ?」
シオンさんの顔色はビックリするほど悪い。
まるで今にも倒れそうなおじいちゃんみたいだ。
と、シオンさんは僕の耳元に口をよせささやいた。
「ドル君と、二人で後部座席に乗った方が近づけるよ。」
その言葉に僕は思わず赤面した。
そうだ。うまくいけば膝枕だって・・・。
僕はその状態を想像して思わず股間を熱くする。
そんな僕を尻目にシオンさんはミールさんを助手席に移すと自分は運転席に乗り込んだ。
「先輩、いけますか?」
「・・・ああ。」
肩を貸すようにして僕は先輩と車に乗り込む。
先輩の腕や胸が僕の背中に触れる。
それだけで僕はドキドキだった。
SAから車に揺られること2時間弱。
やっと、海が見えてきた。
「先輩、海ですよ、海!」
「そんな珍しいもんでもねえだろ。」
と、口では言いつつも僕の肩を抱くようにして身を乗り出し、
僕のよこから窓の外を覗いている。
あ、肩が当たってる。
「もう着きますよ。」
その言葉どおり、それから十数分で僕達は目的地に到着していた。
海岸近くの駐車場に車を停め、三人で荷物を降ろす。
ミールさんは何とか意識を取り戻したものの、気分が優れないようで木陰で休んでいた。
「大丈夫ですか?」
僕の言葉にミールさんは目だけこちらを向けると、
ゆっくりと腕をあげ、弱々しくパタパタと手を振った。
そうとうまいっているらしい。
ドル先輩が肩をかして、なんとか立ち上がる。
それを見た僕の心にむずがゆいものがわきあがる。
暗い、どろりとした感情。
それを抑えるように僕は車から運び出した荷物を抱える。
シオンさんと手分けしてすべてを抱えると僕らは手近な海の家へと向かった。
いったん腰をおろしミールさんの回復を待つ。
「もう車は嫌だ・・・。」
なんとか落ち着いたらしいミールさんはそう呟いた。
見ればドル先輩もシオンさんも苦笑を浮かべている。
僕、そんなへんなことしたかなあ・・・。
荷物を海の家で預けると水着を持って更衣室へと向かう。
更衣室、といってもコインロッカーがいくつか並んだ簡単なもので、個室があるわけでもない。
これじゃあ丸見えだなあ・・・。
そんなことを考えながらふと隣を見れば服を脱ぎ始めているドル先輩の姿。
こ、これは・・・先輩のストリップ!
僕の心拍数が一気に上がる。
先輩の手がズボンにかかった。
ごくり、とツバを飲み込む。
「そんなに気になるのか?」
突然聞こえた先輩の声。
僕が見ているのに気づいて、ニヤニヤと笑いを浮かべながらそう言ってきた。
「あ、いや・・・。」
僕がどう弁解しようかと考えている間に先輩はズボンとパンツを一気におろした。
僕の眼前に晒される、黒く太いだらりとしたモノ。
先輩と“した”時は暗かったためよくわからなかったけど、これは相当立派だ。
にぎりごたえが凄そうだ・・・。
そんなことを考えながら思わず見つめてしまう。
先輩は僕に軽く見せつけるとすぐに水着を身に着けた。
ちょっと残念だったが水着もまた凄い。
前は重要な部分を隠す最低限の布しかなく、後ろに至っては紐が通った程度。
しかも先輩は大きいから今にもはちきれんばかりだ。
「欲しいんならいつでもやるぞ。」
先輩は僕の尻をなで上げるとそのまま先に更衣室を出た。
どうしよう・・・しばらく着替えられない・・・。
なんとか静まるのを待ち僕は水着に着替えると三人が待っている部屋に戻った。
「すいません、お待たせしました。」
僕は小走りで三人のもとへ駆け寄る。
「いや、かまわねえけど・・・お前スクール水着って。」
「変ですか?」
僕がはいているのは高校時代から愛用している黒いスクール水着。
あんまり泳ぎに行くこともないからまだ十分はける代物だ。
ちょっと股間の生地が弱くなってきたかな?
「ミールさんのほうが凄くないですか・・・?」
ミールさんは普通の赤い競泳タイプの水着。
しかし、問題は手にもった大きな浮き輪。
「ああ、これ?僕泳げないから。」
いや、だからってそのサイズは・・・1m越してますよ?
「まあ、とにかく浜辺に行こうか。」
そう言うシオンさんはおそらく一番普通の格好だ。
緑色のトランクス型の水着を無難に着こなしている。
タテガミを後ろで一つに縛っている姿がどことなくかわいらしい。
そういえば昔から寝るときは縛る癖があったっけ。
ぞろぞろと四人で移動すると、砂浜の適当なところに敷物を広げビーチパラソルをさす。
「さ、泳ぐぞ!」
そういってドル先輩は1人海へと駆け出す。
「あ、待ってくださいよ!」
僕も慌ててその後を追う。
「体操しないと身体に悪いですよっ。」
そんな僕の言葉も聞かず先輩はドンドン海の中へと入っていく。
しょうがなく僕もその後に続く。
全身をひやりとした感覚が包む。
「先輩、待ってくださいよっ!」
僕は全身で飛び跳ねると一気に先輩の背中に飛びついた。
「うおっ。」
バランスを崩し、二人で一気に海の中へと沈む。
しばらく海の中でもがいた後、僕達は海面に顔をだした。
僕と先輩は顔を見合わせて笑う。
「おーい。」
巨大な浮き輪がぷかぷかと近づいてくる。
よくみればそこからちょこん、と乗ったミールさんの顔が見える。
僕達が既に足の届かないところまで来ているせいで、
ミールさんは浮き輪につかまってなんとかコッチまで泳いできている。
それを見たドル先輩がニヤリと笑った。
何事かと思った瞬間にドル先輩はその場で息を吸い、海に潜る。
僕もそれに続いて海の中へともぐった。
ゴーグルをつけているので目は痛くないが、あまり綺麗でない海は
全体として緑色に覆われていてよく見えない。
それでもドル先輩の動きが見えた。
先輩はもぐったままミールさんの下半身に近づき・・・水着に手をかけるとそれを一気に取り去った。
ミールさんの下半身が完全に露になる。
やや離れていることと、水が不透明なことでよくわからないが皮のしっかり剥けたものが見える。
息が続かなくなりいったん海面に戻る。
「ドル、返せよーっ。」
必死でミールさんがドル先輩から水着を奪おうとするが、浮き輪ではドル先輩の動きに追いつけない。
「ポン太、逃げるぞっ。」
先輩は僕の腕をつかみ、再び海の中へともぐった。
僕は咄嗟に息を吸いそれに備える。
海の中に潜ると、目の前にミールさんがいた。
先ほどよりもより近くにいるためはっきり見える。
皮のむけきった雁高なモノ。
ドル先輩よりは小さいかな・・・。
先輩に手を引かれミールさんから離れる。
どうして隠さないんだろうと思っていたが、離れてみてやっとわかった。
浮き輪に捕まっているために股間に手が届かないのだ。
「返せってばー!」
海面ではミールさんが叫びながら必死でバシャバシャとやっている。
なんか哀れ・・・。
「欲しかったらこっちまできなっ。」
そう言ってドル先輩は更に遠くへと泳ぐ。
先輩の笑顔は、とても楽しそうだった。
「ふぅ。」
僕は1人砂浜まで戻り、敷物の上に腰を下ろした。
ドル先輩とミールさんの鬼ごっこも一息ついて、ようやくミールさんも水着を取り返した。
ドル先輩は水着を放すと今度は1人でさっさと海岸でナンパをはじめてしまった。
僕はミールさんに砂浜まで引っ張っていこうかとたずねたが、
1人で泳ぐからいい、という。
結果僕は1人で戻ってきていた。
「堪能したのかな?」
1人荷物番で残っていたシオンさんがゆっくり起き上がりながらそう尋ねてきた。
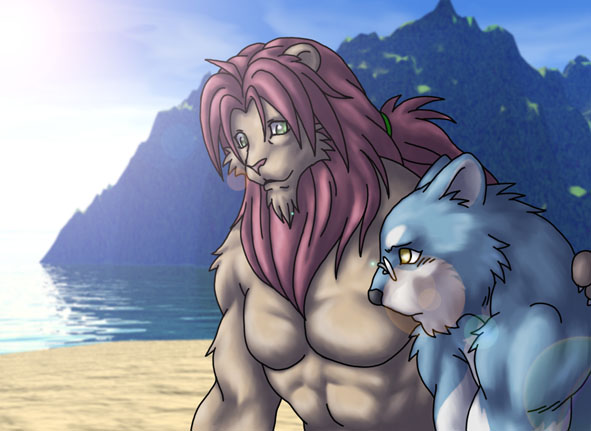
「ええ、まあ・・・。
それよりすいません、荷物番押し付けちゃって。」
「いや、構わないよ。」
シオンさんは笑顔でそう答えてくれた。
堪能したと言えば堪能できただろう。
先輩とこんなに遊んだのは初めてのような気もする。
ホントのことを言えば二人で遊びたかった気もするけど・・・。
「それにしても、何も皆出来てるときにナンパしなくったっていいだろうに・・・。」
「『僕といるときに』の間違いじゃないのかな?」
僕が不満そうに呟くと、シオンさんがからかうようにそう言ってきた。
言葉に詰まってシオンさんの方を見る。
さわやかな笑顔が僕を攻め立てていた。
「そんなつもりは・・・少しは、ありますけど・・・。」
思わず赤面したのが自分でもわかる。
僕は慌てて視線をそらした。
後ろでシオンさんが声を殺して笑っている。
「堂々と笑っていいですよ。」
僕はちょっとスネながらそういった。
「いや、ごめんごめん。ホントに、昔と変わらないね。」
成長してないってことかなあ・・・。
「シオンさんのイジワル・・・。」
「ははは、だから悪かったよ。」
そういってシオンさんは僕の頭をぐりぐりと撫でた。
気持ちイイ・・・。
これだけで機嫌を直してしまう僕も現金だなあ・・・。
ふと見れば、ドル先輩が女のヒトに強烈なビンタを喰らっていた。
夜。
昼間さんざん海で遊んだ僕らは、既に僕お勧めの旅館に到着していた。
遊びすぎたせいか体中がいたむ。
「先輩〜疲れた〜。」
布団を引きずり出し横になっている先輩にじゃれ付く。
触った胸は筋肉が張り出した、立派なものだった。
「重い〜。」
先輩は僕を振りほどこうとするが僕は先輩にしがみついたまま離れない。
なんだかんだでもみ合ってるうちに、僕は先輩に組み敷かれる形になった。
先輩と目が合い、胸が鳴る。
言葉が出せない。
「悪いけど、じゃれるなら二人になったときにしてくれない?」
ミールさんが横から冷めた声を投げてきた。
「べ、別にじゃれてるわけじゃ・・・。」
僕は顔を赤くしながら慌てて先輩から離れる。
先輩は本当に疲れきっているらしくその場にべたりと倒れこんだままだった。
二人部屋だったらじゃれ放題だったかなあ・・・。
「それより、そろそろお風呂にでも行きませんか。ここは露天風呂が有名みたいですよ。」
シオンさんは話題をそらすようにそう言った。
なんだか今日は気を使わせてばっかりだなあ・・・。
そう重いながら僕らは風呂の準備をして脱衣所へ向かう。
幸い僕らの部屋から露天まではすぐ近くだった。
「入るぞ〜。」
先輩は素早く服を脱ぐとそのまま一気に走っていった。
「こけますよ。」
僕の言葉も先輩には届かない。
僕は小さく溜息をついて、先輩がかごの中に投げ入れた服をたたんだ。
続いて僕も服を脱ぎ、腰にタオルを巻く。
僕は表への扉をくぐると先輩の姿をさがした。
「あれ・・・?」
先輩の姿が見当たらない。
と、突然僕は後ろから羽交い絞めにされた。
「せ、先輩?」
「ポン太〜。ダメだぞ、こんなもんで隠しちゃ。」
そう言って先輩は器用に足で僕のタオルを取り去った。
僕の股間が湯船に向かって全開となる。
「やめて下さいよ〜っ!」
ふと、僕の尻に何かが当たる。
先輩の腕は僕のわきの下を通り肩を抑えている。
足は両方地面に着いているし先輩の尻尾は短いから前までまわるはずもない。
じゃあ・・・この僕のお尻の辺りにある柔らかいけどなんとなく芯がとおったようなものは・・・。
当たっている。
それに気づいた瞬間僕のモノに力が入り始めた。
先輩もすぐにそれに気づいたらしい。
「お、何たててんだお前。」
そう言いながら先輩は片手で僕のモノをつかんだ。
「んっ・・・。」
快感に声が漏れる。
それを面白がってか先輩は更に手で僕を攻める。
「ちょ・・・人前なんだから、やめて・・・あっ・・・。」
どうしても喘ぎ声が混じってしまう。
恥ずかしいっ!
いつのまにかミールさんもシオンさんもこちらを見ていた。
「へえ、じゃあ人前じゃなきゃいいんだな。」
そういって先輩はにやりと笑った。
いつのまにか僕の尻に当たるモノも熱く、硬くなっている。
もしかして先輩、犯る気マンマン?
「た、タスケテ〜。」
僕はなんとか先輩を振りほどくとシオンさんに飛びついた。
「うわっ。」
予期していなかったのかシオンさんはその場にしりもちをつく。
衝撃で、手にしていたタオルを落としシオンさんも股間を露出してしまう。
あ、半立ち。
「何興奮してるんですか。」
そう言って僕はシオンさんのモノをつかんでしごき上げた。
「バ、バーツ。ダメだよ、そんなこと・・・。」
シオンさんは必死で止めようとするが半分持ち上がっていたものはあっという間に天を衝く。
「ドル〜、それしまいなよ。」
向こうでは1人温泉につかったミールさんが冷めた目で先輩をみながらそう言っていた。
「うるさい、こうなったらお前も道連れだ〜。」
「ちょ・・ドル、やめて〜。」
何がこうなったらなのかよくわからないけれど。
先輩はミールさんを湯船から引きずり出すと自分の膝の上に座らせるようにして、ミールさんのモノを扱き出す。
ミールさんは必死で抵抗するが力はドル先輩の方が強い。
あっという間にねじ伏せられ、勃起させられてしまった。
結局、四人とも立ち上がったモノを揺らしながらその場に立つことになった。
他の客いなくてよかった・・・。
「よし、こうなったら大きさ比べだな。」
先輩がミールさんを引きずるようにして僕とシオンさんの所にやってくる。
僕とシオンさんは半ばあきらめたように、ミールさんは強引にその場に竿を並べる。
勃起した竿が四本並ぶのは異様な光景だった。
まあアダルトヴィデオなんかで見ることはあるけれども・・。
ちなみに。
一番大きいのはドル先輩だった。
太さ、長さともに四人の中で一番を誇っている。
まさに男なら憧れる立派な巨根だった。
次が僕。
その後にシオンさん、ミールさんと続く。
ぼ、僕はシオンさんより大きかったのか・・・。
「次は飛距離だ〜。」
先輩は終わったと思い油断していたミールさんを素早く捕まえると一気に竿をしごき始める。
「そ、それだけは勘弁して〜。」
だがドル先輩は容赦なくミールさんを攻め立てる。
ドル先輩の手で感じるミールさん。
僕は悔しくなり、手にボディーソープをとると先輩の手からミールさんのモノを奪い取った。
ゆっくりとそれを塗りつけるように手を上下させる。
「ぽ、ポン太・・・やめ・・・ああっ。」
ミールさんはさっきより更に感じ始める。
やはり潤滑油の存在は大きいらしい。
先輩の手で感じさせるのが嫌だったから奪っただけだったけれど、
最後までやらないことには先輩が継続してしまうことに今更ながらに気が付いた。
しょうがなく、ミールさんが果てるまで僕は付き合うことにする。
「あっ・・・やあっ、でちゃうっ。」
ミールさんの竿がひときわ大きくなる。
びくんびくんと振るえながら先端から先走りが排出され、絶頂が近いことを物語る。
「よーし、ミール。しっかり飛ばせよ!」
先輩の言葉に僕はミールさんのモノの角度を変えながら一気にしごいた。
「で、出るーっ!」

びくん、と僕の手を跳ね除けそうなほど大きく跳ね上がった。
それと同時に白い液体が遠くまで飛んでいく。
2mは飛んだんじゃないだろうか・・・。
「凄い・・・。」
その間にもミールさんは大量の液体を吐き出していた。
「他の人がきそうですよ。」
突然聞こえたシオンさんの声に脱衣所を見ると、確かに人影があった。
僕らは慌てて後始末をすると湯船に飛び込んだ。
「なんで僕だけ・・・。」
ミールさんは湯船のなかで1人嘆いていた。
そして、深夜。
僕は皆が寝付いたのをみて、1人部屋を抜け出して中庭を散歩していた。
あたりは緑が生い茂り、とてもここちよい匂い。
空には少しかけた、十六夜月。
うっすらとした明りが僕の全身を包む。
「楽しかったなあ・・・。」
僕は今日一日の出来事に思いを馳せる。
皆で車に乗り、走ったことも。
海で泳いだこと。
皆で食べたご飯。
一緒に入ったお風呂。
四人での旅は、どれもいい思い出だ。
「眠れないのか?」
突然声がする。
振り返ってみると、一番に眠ったと思っていたドル先輩。
「先輩・・・。」
先輩がゆっくりとこちらに向かってくる。
先輩は僕の隣に立つと、僕が見ていたように月を見上げた。
しばらく先輩の横顔を見つめ、僕も再び月を仰ぐ。
「先輩・・・。」
僕の呟きに先輩は答えない。
だけど、続きを待っているのはなんとなくわかった。
「とっても、楽しかったですね。」
僕の言葉に先輩は小さく頷いた。
僕の言葉を待っているようだ。
僕が、何か言いたいということを察しているんだろう。
「・・・。」
だけど、いえない。
意気地がない。
これが最後のチャンスかもしれないのに。
「僕・・・僕、先輩のことが・・・。」
そこまで言って、どうしても続きがでない。
怖い。
だけど、言わなくちゃ。
言うって決めたんだから。
この旅を始める時に。
「先輩のこと・・・・・・・・・・・・・・好きです。」
顔を真っ赤にして、僕はその言葉を搾り出した。
先輩はその言葉にこちらを見ている。
予想外だっただろうか。
それともわかりきったことだっただろうか。
恥ずかしくて先輩の顔を見ることが出来ない僕には判別がつかない。
「返事とか、そういうのはいいですから。
いいたかった、だけですからっ。」
僕はまくし立てるようにそう言うと先輩を置いて走り出した。
結局、先輩と殆どしゃべることなく逃げるように僕はその場を後にした。
次の日は帰るだけだ。
皆で荷物を積み込み車に乗り込む。
運転手はシオンさん。
そして、助手席は僕。
僕が自分からその席を選んだ。
シオンさんは「おや?」という顔をしていたけど、今は先輩と顔を合わせるのが怖かった。
車の中でも寝たふりを続け、できるだけ先輩と話さないようにして僕は家に戻った。
「ふう・・・。」
家に戻り、ベッドの上に倒れこむとどっと疲れが出る。
とても疲れたけれど、四人で作った思い出はとても楽しいものだった。
アメリカに行くために、一番大切なものを準備できた気がした。
他の着替えやなんかはすでにカバンに詰めてある。
パスポートも持ったし、勉強用の道具だって忘れちゃいない。
バイトももう辞めてきた。
もう、先輩に会おうと思わない限りは会うことはないだろう。
僕たちが顔をあわせていたのはバイトの場面がほとんどだ。
それでも、先輩と二人でいられる時間があることは僕にとって非常に嬉しいことだったけれど。
昨日、もう告白してしまったのだ。
もう元には戻れないだろう。
それならいっそ会わないほうが気は楽だ。
僕はそう思いながらそのままベッドの上で意識を手放した。
どこかで音が聞こえる。
ドンドンと何かをたたく音。
ふっと目を覚ませば、誰かが僕の家の扉を激しくノックしていた。
「あ、ごめんなさい。今でまーす。」
僕はそう叫ぶと鏡を見てよだれの跡がないことを確認して扉を開けた。
扉の向こうには見慣れた姿。
「ドル先輩・・・。」
どこか怒ったような表情を浮かべた先輩が立ってた。
僕が口を開こうとする前に先輩は一人でさっさと僕の部屋の中に入ってくる。
僕は冷蔵庫からお茶を取り出すと先輩にさしだした。
「バイト辞めたんだってな。」
先輩が切り出す。
その話か・・・。
「色々お世話になったのに挨拶できなくてすいません・・・。
どうしても、やめなくちゃいけない都合ができてしまって・・・。」
僕は口ごもる。
先輩が視線でその都合のことを促しているが、どうしても口に出す勇気がない。
「その・・・アメリカに・・・行くことになったんです。」
「アメリカ?」
僕が何とかそういうと、先輩は驚いたように聞き返してきた。
「学校の先輩に誘われて・・・一緒に向こうで本場の医学を学ばないかって。
それで、いくことにしたんです。だから、もう・・・」
僕はあふれそうになる涙を必死でこらえていた。
先輩に会えなくなるのだ。
どうしてアメリカに行くなんて言ってしまったんだろう。
先輩が振り向いてくれなくても、他のヒトを見ていても。
そばで憧れることしか出来なくても。
やっぱり僕は先輩のそばがいい。
涙でにじむ視界に先輩の顔が見えた。
その顔はゆっくりと近づいて、僕にキスをする。
「先輩・・・?」
先輩は無言で僕をベッドに押し倒した。
身に着けていたシャツが剥ぎ取られる。
僕は先輩に抱きついた。
先輩も無言で抱き返してくれる。
こらえていた涙があふれてきた。
「せんぱい・・・。」
先輩の手はすでにむき出しになった僕の股間を捕らえている。
直接的ではあるが、やさしい愛撫。
僕は体も心も興奮していた。
先輩が、自分の意思で僕を抱いてくれる。
依然とは違う先輩の意思。
もう会えなくなる、同情なのかもしれない。
それでも、先輩は僕のことを抱いてくれる。
どこから取り出したか、ローションを手に取ると先輩は僕の尻に塗りだした。
「初めてか?」
先輩の言葉に僕はうなづく。
誰にも触らせたことのない場所。
ローションを借りて、先輩の指が僕の中に侵入してきた。
「はぁっ・・・。」
きつい。
だけど、先輩だから許して良いと思う。
二本、三本と少しずつ増えていく。
「せんぱぁい・・・。」
さすがに三本はきつく、僕は先輩に泣きつく。
先輩は無言で僕に口付けをする。
先輩の舌が僕の舌を捕らえる。
そうやって僕の気をそらしている間に先輩は僕を少しずつ拡張していった。
「ポン太、もう入れて良いか?」
そういいながらすでに先輩のサオが僕の入り口にあてがわれていた。
僕が頷くと、そのまま先輩は一気に進入してくる。
「先輩、いたいっ!」
だが一気に進んだため、すでに先輩の腰が僕の尻に密着している。
僕がなれるまで先輩はそのままじっと待っていてくれた。
「ポン太・・・。」
先輩の言葉に僕は先輩を見つめる。
「俺は・・・恋人だとかそういうのはできねえけど。」
先輩は小さく僕にキスをする。
「今は。少なくとも今はお前だけだ。ポン太。」
そういって、照れを隠すように先輩は腰をゆっくりと動かし始めた。
「先輩・・・先輩・・・。」
ゆっくりと先輩が僕の内部を侵食し始めた。
太く長いものが僕の内部をどんどん押し広げていく。
初めてだから痛みは相当なものだ。
それでも大好きな先輩にこうして抱かれているのだと思うだけで僕は満足だった。
「先輩・・・きもちいい?」
僕の言葉に先輩は息を荒げながら頷いた。
嬉しい。
僕は先輩が満足してくれたら・・・。
そう思うだけで僕は快感を感じることが出来た。
それだけで僕は張り詰めた先端から体液をこぼしていた。
「先輩、僕もうイく・・・。」
だが先輩は首を横に振った。
「ポン太、まだイくな。」
「でもっ・・・。」
僕は必死でこらえていたが、それでももう限界が近い。
僕のモノが僕と先輩の間でびくびくと震えている。
「ポン太、イくなよ・・・イくな、行くなポン太・・・。」
先輩が僕を強く抱きしめる。
「行くな・・・。」
先輩の言葉はどこか優しかった。
「駄目です、もう、イくっ!」
「俺もイくぞっ!」

言葉のとおり、先輩は僕が達したのを追いかけるように僕の体内に精液を吐き出した。
僕は先輩を起こさないように服を着替えると、先輩に置手紙を残し荷物を手に取った。
今日が、アメリカへ発つ日。
直前に先輩と愛し合えたことはこれ以上ない幸福だ。
僕は眠った先輩にキスをして、部屋の扉を開けた。
「帰ってきたら連絡しろよ。」
ベッドに寝そべり、僕に背中を向けたまま先輩はそう言った。
寝たふりをしていたのだろう。
ありがたかった。
今顔をあわせても、僕は泣き顔しか見せられない。
「先輩、お体に気をつけて。」
僕の言葉に先輩は答えなかった。
そのやさしさに思わず僕の目から涙がこぼれる。
泣き顔を見せないようにするために、僕は部屋を出る。
「さよなら。先輩。」
最後まで、先輩は返事をすることはなかった。
先輩の気遣いが、とてもありがたかった。
日がのぼったばかりの空は、憎いほどに清々しかった。
一週間の時が流れた。
日常から欠けたものに少しずつ慣れだした頃。
「シオンから話があるなんてめずらしいじぇねえか。」
そう言いながらドーベルマンはウェイターにコーヒーを注文する。
獅子も同じものを注文すると、目の前のドーベルマンに向かって口を開いた。
「実は・・・相談が・・・。」
「相談?」
獅子は真剣な顔で頷く。
そして、ある一点を見つめてその顔が凍りついた。
「どうした、鳩がマシンガン喰らったみたいな顔して。」
ドーベルマンは獅子の視線を追うように後ろを振り向く。
彼もまた獅子と同じように凍りつく。
「ポン太・・・?」
「ドル先輩、ただいま戻りましたっ!」
僕はふざけて敬礼をしてみせる。
「お前アメリカいったんじゃねえのかよっ!」
「え?もう終わりましたよ?」
僕の不思議そうな顔に先輩は口をあんぐりとあけている。
そんな変なこといったかな・・・?
「バーツ・・・終わったって・・・留学したんだろう?」
シオンさんが先輩に代わって口を開く。
「え、留学ってほどのもんじゃないですよ。
向うで三日間ほどえらい先生が講演会開くって言うんで、それを聞きに言ってたんです。
すごい面白かったですよ。」
ひょっとして・・・先輩も留学するって勘違いしてたのかな?
もともと5泊くらいで帰ってくる予定だったんだけど。
「先輩・・・?」
下を向いて手を握り、全身をぷるぷると振るわせている。
僕は先輩の顔をしたから覗き込むようにして表情を伺う。
「それならそうと早く言えバカ野郎っ!」
突然そう叫ぶと先輩はそっぽを向いてしまった。
うう・・・怒られた・・・。
僕はおもわずしゅん、と下を向く。
「ああいってるけど、バーツがいなくなってからずいぶんと寂しそうにしていたんだよ。」
驚きから立ち直ったらしいシオンさんが、笑顔でそう言った。
こういうところでフォローを忘れないのがシオンさんらしい。
それにしても・・・、寂しがってくれてたんだ。
「先輩、寂しがらなくても大丈夫ですよ。
僕は先輩のそばをずっと離れませんから!」
僕は笑顔を浮かべ、後ろから抱きつくようにして先輩の顔を覗き込んだ。
先輩は何も言わなかったが、その顔には苦笑が浮かんでいる。
無言のまま先輩は僕の頭をわさわさと撫でてくれた。
また、先輩との日常が始まる。
以前よりは少しだけ前に進んだ日常。
そんな日常に、僕はウェイターが持ってきたコーヒーで、
大きく胸をはりひとり堂々と乾杯をした。
完